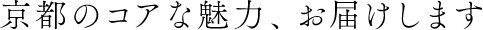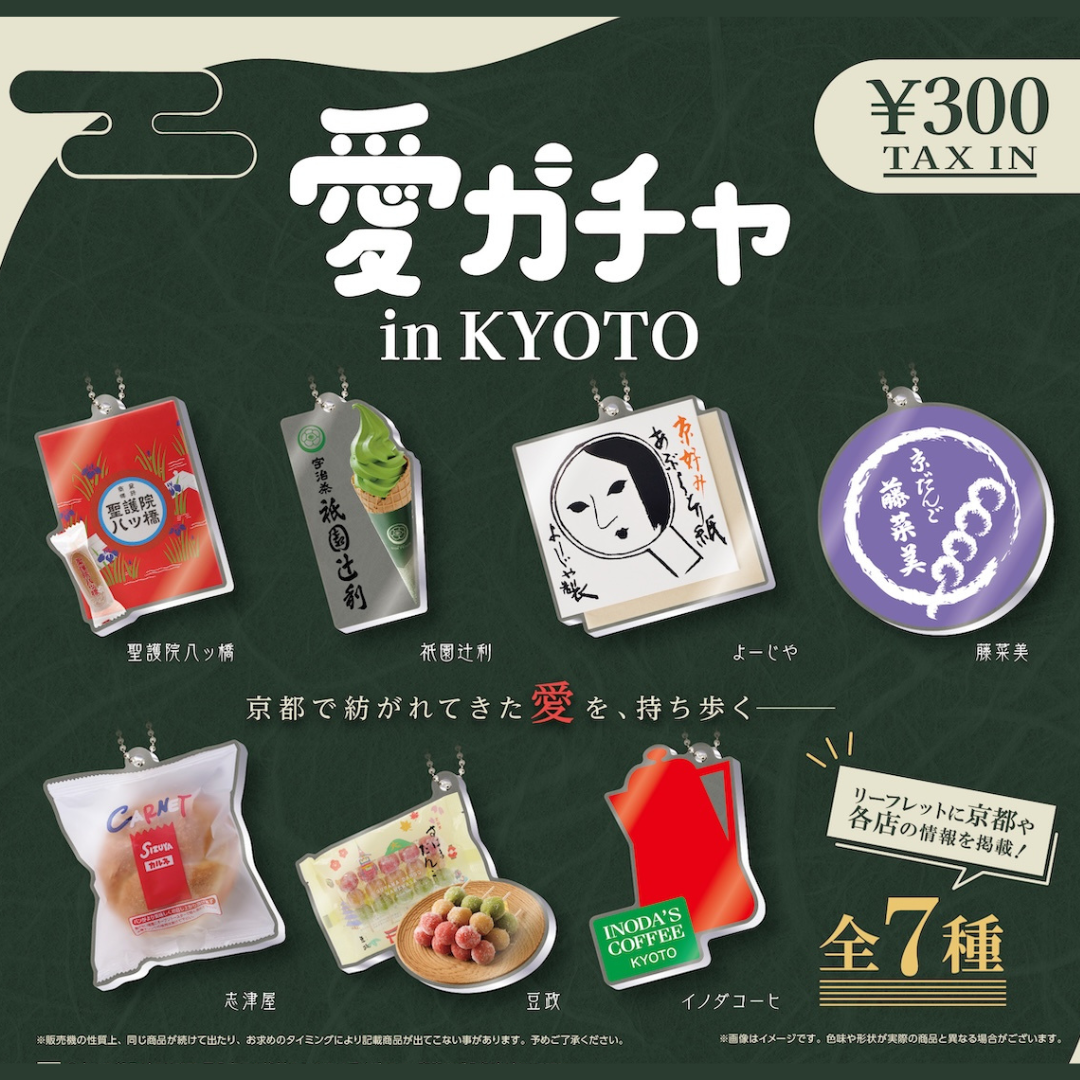食べる
つくる
つくる食べる#学びの秋。京都の伝統技術に触れよう

2023.09.08 東林院
精進料理を通して日々の暮らしと向き合おう
肉や魚を使わず、旬の野菜や山菜を無駄なく使う精進料理。というと敷居が高く感じるかもしれませんが、決して難しいものではありません。素材そのものの味と香りを引き出すよう少しの工夫をして調理する、いわばお寺のおばんざいです。
『誰にでもできる精進料理』(淡交社)などを著書にもつ東林院の西川玄房住職が指導する体験教室では、家庭でも取り入れやすい献立で、楽しくおいしく精進料理を学ぶことができます。

料理教室は週2日。月替わりの献立から、3品を参加者たちで作ります。7月の取材時はオクラとトマトと厚揚げの葛とじ、枝豆の納豆揚げ、もずく・きゅうりなどのごま酢和えを作りました。
まずは住職の談話から。精進料理の心得とレシピの説明があります。
大切なのは、その時の旬の食材を丁寧に使い切ること。調理の際には、無駄を省くこと。「電気もガスも水も、その時に応じて必要な分を、正しく活用することが大切」。住職の言葉を頭において、配られたレシピと材料を確認しながら調理の段取りをイメージします。

いよいよ調理開始。ここでは手取り足取り作業を教えられることはありません。4、5人ずつに分けられた班ごとに、自分たちで分担し、効率を考えながら調理します。教室にはリピーターの方も多く、リーダーシップを取って手際よく進めてくださるので安心です。
今回は冷やす時間が必要な葛とじから仕上げていきます。色合いがきれいで夏らしい一品になりそう!

こちらは枝豆の納豆揚げ。納豆を粒がなくなるまですりつぶし、ピーナツバターのような形状に。小麦粉をまぶした枝豆を加え、一口大ずつすくって揚げていきます。納豆をここまですりつぶすのに少し時間はかかりますが、これこそが、素材の味と香りを引き出すための工夫。どんな料理になるか楽しみです。

「酢の物は水気が出るから食べる直前、ぎりぎりに和えること。」「懐紙が油を吸ってべたべたになるから納豆揚げの盛り付けはもう少し後で。」
調理後半に住職のアドバイスが入りつつ、3品揃ったところでいよいよ人数分を盛り付けます。
住職お手製の数品と汁物が加わり、見事な精進料理膳のできあがり。お庭を眺めながらいただきます。
食材一つ一つはいつも食べている身近なものなのに、一口噛みしめるたび、心身に染み渡る味わい深さを感じます。

食後には、再び住職の談話タイム。住職がいつも念頭においているのが、「自分の四方30km以内のものを食べなさい」という古くからの言い伝えだそう。それはつまり、住んでいる土地の土と水、空気で育った旬のものが、一番自然体でその人の体に合っているということ。この考え方こそ、全国各地、年中何でも手に入る現代において忘れてはならない日本の食文化の原点であり、精進料理の考え方であると住職は語ります。
仏教用語の「三昧(ざんまい)」についてのお話もありました。三昧とは、精神を集中し、雑念を捨て去ること。修行のひとつでもある「食」においては、食材はもちろん、それを作る人、あるいは食べる人の命を思い、決しておろそかにせず集中して調理・食事を「やりきる」ことが大切で、それが自然の営みや恵みに感謝することにつながるといいます。
「お家でも、テレビやスマホの電源を切って、「食三昧」の時間を過ごしてみると、自分の暮らしを見つめ直すきっかけになるかもしれません。」

東林院は、庭の沙羅双樹が美しい妙心寺の塔頭寺院。通常参拝はできませんが、季節ごとに期間限定で一般公開されています。
2023年10月13日(金)~22日(日)の10日間は、夜間特別拝観『梵燈(ぼんとう)のあかりに親しむ会』を開催予定。住職手作りの瓦の燈篭「梵燈」の灯りが境内に揺らめき、幻想的な世界が広がります。訪れた際は、奥書院の庭にある水琴窟の美しい音にもぜひ耳を傾けてみて。

Informations
京都市右京区花園妙心寺町59
TEL:075-463-1334
※通常公開はしていません。
◎市バス「妙心寺前」下車、徒歩約5分
*精進料理教室
日時:火・金曜10:00~13:00
料金:1人3,600円(税込)
持ち物:エプロン、筆記用具
予約:電話で予約の上、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、希望日時、参加人数を記入し申し込み。
*梵燈のあかりに親しむ会
期間:2023年10月13日(金)~22日(日)
時間:18:00開門~21:00閉門(入山は20:30まで)
料金:拝観料700円、茶席(抹茶、菓子付)600円(税込)