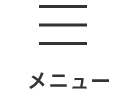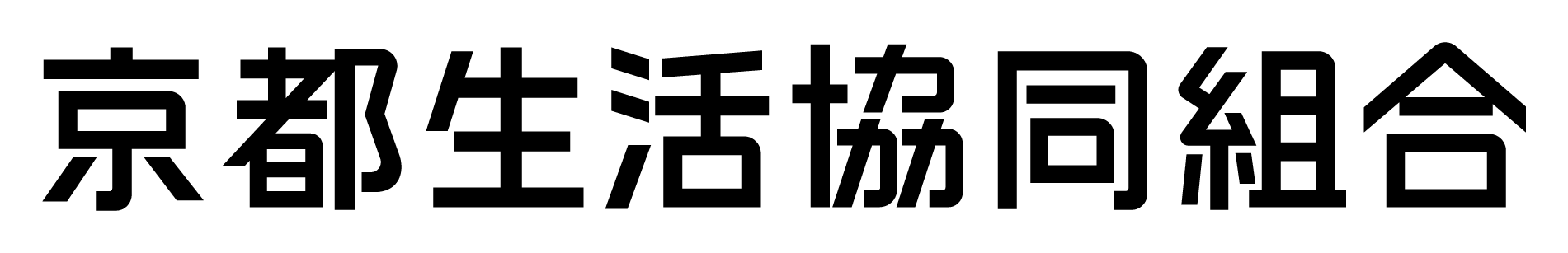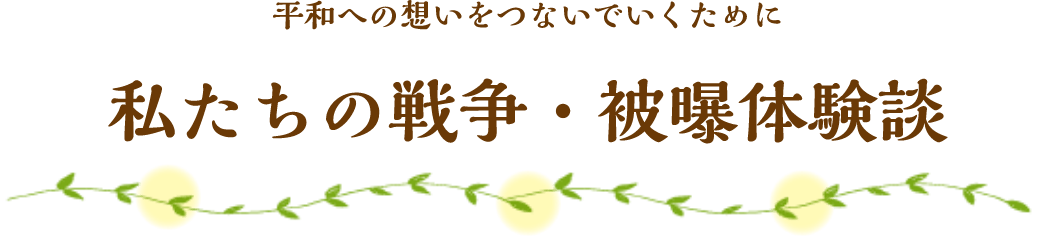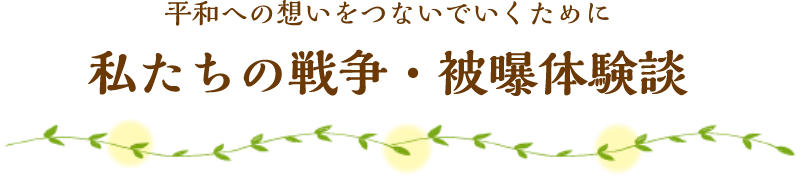戦時中の辛い体験談に耳を傾けて藤原真由美さん
- 疎開
- 暮らし
- 終戦
両親から疎開の話を聞いたことがあります。
父は東京で生まれ、戦争が激しくなった小学5年生の時に、親戚がいる京都府船井郡に疎開しました。周りは山ばかりで、唯一あった郵便局で仕事を手伝っていました。一晩中歩き続けて山を越え、電報を届けたこともあったそうです。
父は船井郡から東京の家に一時的に戻り、家族が揃い次の疎開の準備をしていた時に終戦を迎えました。
終戦から3日後、零戦が「政府は降伏したが、我々は最後まで戦う!」というビラを空から撒き、それを警察が素早く回収していたそうです。
その後、開拓のために家族で宮崎県に移り住みました。父は中学へ入学後、しばらく机と椅子ばかり作らされて授業は受けられなかったそうです。
母は京都市内で生まれ、昭和20年3月に綾部の中筋に疎開しました。京都駅では遠足気分の子どもたちに対し、親は最後のお別れかもしれないと泣いたそうです。母を含む身体の丈夫な子どもたちは一番遠い安場公会堂で生活しました。晴れの日はわらじを履いて、雨の日は裸足で登校しました。京都市内では白米は貴重でとても食べられませんでしたが、綾部では白いご飯をいただいたそうです。
終戦の日は大切な話があると知らされ、正午にラジオの前に座っていましたがよく聞き取れず、翌日の新聞で日本が負けたことを知りました。先生が「君たちがかわいそうだ」と言って泣き出したので、つられて子どもたちもわんわん泣いたのでした。
それから2カ月後にやっと京都市内へ帰り家族と再会しましたが、食糧はなく、鴨川に行って雑草を採ったり近所に食べ物を分けてもらったり、祖母の着物を手放したりして生活したそうです。たんすからどんどん着物がなくなっていくのを見て、子どもながら心がとても痛んだのを覚えているとのことでした。
私の両親は高齢ですが、子どもの頃の辛い体験があって今の姿があるのだと改めて思いました。便利な物に囲まれた生活が当たり前となっている今、戦争を体験した方々の話に耳を傾け、関心を持ち続けることが大切だと思います。