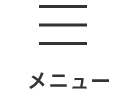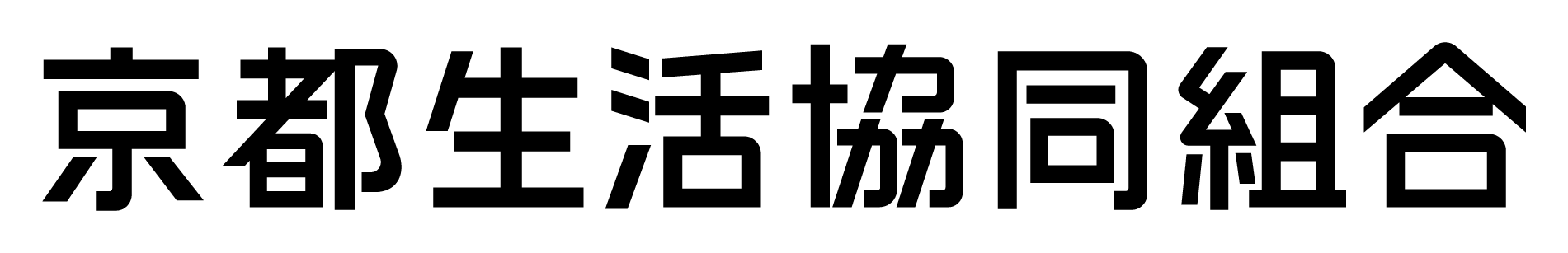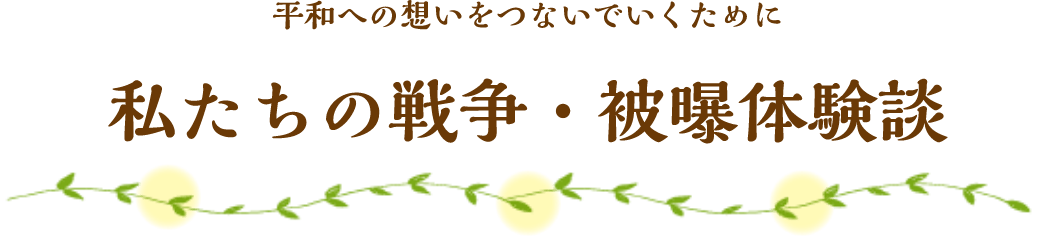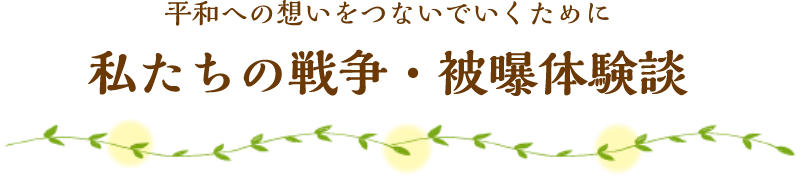原爆投下からの十日間吉沢保枝さん
- 被爆
- 学徒動員
昭和20年(1945年)1月から、私たち広島女子専門学校数学科1回生は、岡山県倉敷市郊外にある三菱重工業水島航空機製作所へ学徒動員として駆り出され、海軍の一式陸上攻撃機の部品である風防製作に当たっていた。
8月8日の朝、会社から「6日に広島に空中魚雷という新爆弾が落とされたそうだ。広島から来ている人はすぐ帰りなさい。親や兄弟が生きているとは絶対に思わないでください」という一斉指示があった。寄宿舎生活※を送っていた私たちは、被爆者の看護のため翌朝倉敷を出発、山陽本線が不通のため、中国山地を通る伯備線と芸備線を乗り継いで広島へ向かった。列車はゆっくりと進み、翌日10日の朝、やっと学校に辿り着いた。
学校は爆心地から離れていたため、半倒壊の状態であったが焼失は免れており、すでに臨時の救護所になっていた。爆心地に勤労奉仕に行っていた県立第二女学校の生き残った負傷者と、隣接する陸軍共済病院から溢れてくる、ケガややけどを負った人々でいっぱいであった。
教室では、くっつけた机の上にむしろを敷いた即席ベッドに、多くの負傷者が横たわっていた。あちこちから「水、ミズがほしい……」とうめき声が聞こえてくる。水を飲ませようにも、ほとんどの人が口を開けることもできず、水を吸う力もない。
傷の手当てをしようにも、やけどが化膿したところにつける薬もない。ただ、赤チンキを塗るだけである。どこからともなく飛んでくる蝿を追い払うのも大変なことであった。蝿はやけどした皮膚の上に卵を産み付けるのだ。卵から孵化した幼虫を見つけ次第、ピンセットで一匹ずつつまみとった。赤チンキの赤、膿の黄、蝿の黒の3色で爛れた皮膚は目を覆うばかりであった。
次第に薬も無くなり、脱脂綿も消毒液もタオルも品切れとなってしまった。やけどをしている人たちの体は異臭を放ち、教室は臭気に満ちた。次から次へと、死者が増える。軍の衛生兵らしき人が、学校に隣接したれんこん畑で材木を積み重ねて死体を焼いた。毎日、毎日、死体を焼く臭いが付近一帯に漂った。
3日後、米軍の飛行機が1機飛んでいった。空襲警報も鳴らなかったし、私たちはもう防空壕に逃げ込もうとも思わなかった。つい1カ月前には、水島航空機製作所が100機編隊のB29爆撃機に爆撃され、私たちは雨あられと投下される爆弾の下を逃げ回っていたのに。「戦争に負けた!」と痛感せざるを得なかった。
8月15日。学校の事務室前で玉音放送を聞いた。もう逃げ回らなくても良いのだ!死と向かい合わなくても良いのだ!「戦争が終わった」とは、何と素晴らしいことだろう。
私は青い空を見上げて、何年ぶりかの深呼吸をした。
※広島女子専門学校(現・県立広島大学)は当時、西日本を中心に朝鮮、樺太(サハリン)からの学生が多く、多くは寄宿舎生活を送っていた。