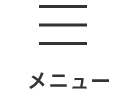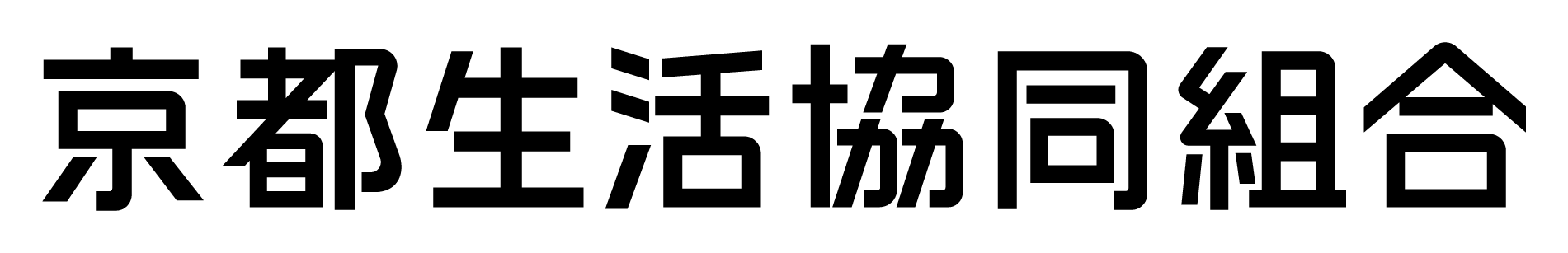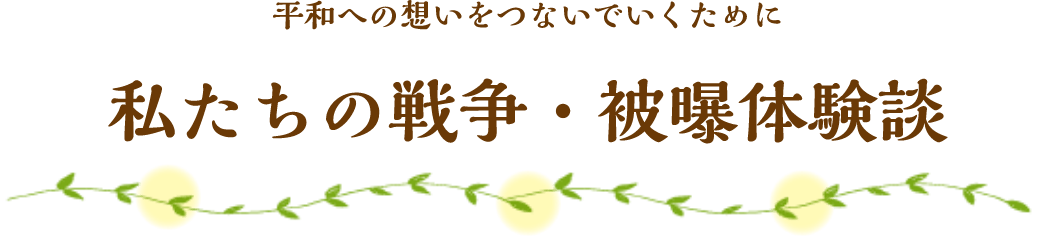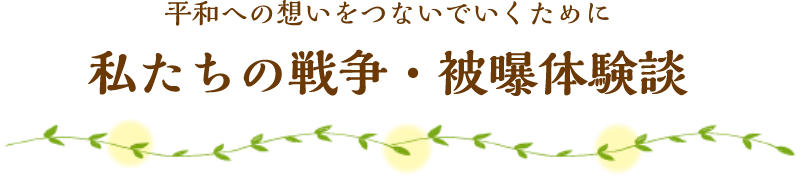父の苛酷な戦争体験藤田和代さん
- 満州開拓移民
- 引き揚げ
2016年9月に96歳で亡くなった父の戦争体験を、子どもの頃から何度も聞いて育ちました。その都度、記録しておけばよかったのですが、当時は「またか」という気持ちで聞いていたので、苛酷な体験に寄り添って聞き取ることができず、今頃になって後悔しています。その中で覚えていることをいくつか書き出してみます。
家は貧乏百姓で、兄は働きに出て消息不明。妹ばかり5人もいる一家の働き手として、京都市内で丁稚奉公をしていた時に「満蒙開拓青少年義勇軍募集」のビラを見て満州行きを思い立った。行けば、土地がもらえる。家族を呼び寄せられると勇んで出かけた。18歳だった。
しかし酷寒の土地での作業はあまりにも厳しく耐え難かった。3年が経過し、現地で徴兵検査に合格、ソ連と満州の国境警備についた。冬は零下30℃にもなり、川の水が凍りついて対岸まで歩いて渡れるので、いつソ連兵が攻めてくるかと厳しい警備であった。
さらに3年が経過し、太平洋戦争に突入。南方戦線が厳しくなってきた頃、冬なのに頭の先から足の先まで夏服が支給された。「これは南方に送られる」と覚悟を決めた。
(これは私が後に叔母たちに聞いた話ですが、父は船で南方に送られる途中、神戸港に立ち寄って、家族と会うことが許されました。父はあらかじめ手紙で知らせてはいたものの、まさか丹波の田舎から家族に会いに来てもらえるとは思わず、「せめて叔父に会いに行こう」と京都へ出かけました。一方、祖父と祖母は長く離れていた息子に会えると思って、田舎から貴重な米で作った握り飯を持って会いに行きましたが、行き違いで会えず、船は出てしまいました。嘆き悲しんだ祖母は泣き崩れ、祖父は息子に食べさせようと思った握り飯を海に投げ込んで悔しがっていたそうです。)
船では米軍の魚雷攻撃を受け、鉄板が刺さって足に大ケガをした。その後、シンガポールからマレー半島、タイを転戦。昼間はジャングルの中で身をひそめ、夜になって進行するが、食料は乏しく、草や木の実など食べられるものはなんでも食べた。飢えと病気で仲間は次々と死んでいく。ジャングルで横になっていると、木の上からヒルが落ちてきて体に吸い付くので手で取ってつぶした。
そして終戦。イギリス軍の捕虜になり、炎天下での溝さらえや土木工事など苛酷な作業をしながら帰国を待った。そんな時にも、中国人の子どもが近づいてきて、そっとズボンのポケットに煙草を入れてくれた。
やがて帰国の時が来た。全員に番号が付けられ、1番から順番に船に乗せられる。「女、子どもが先、兵隊は一番最後」と言っていた。昭和21年6月に佐世保に上陸し、8年振りに故国の土を踏んだ。列車を乗り継ぎ、和知駅からは歩いて家にたどり着いたが、家族はみんな田んぼに出ていて留守だった。
私の姿を見た近所の少年が田んぼまで走って知らせに行き、飛んで帰ってきた両親や妹たちと涙々の再会を果たした。いつまでも泣いている母たちに父が「早う飯を炊いて食わしてやれ」と言って、物置にしまってあった米を出してきた。腹いっぱい飯を食うことができた。
それから後の苦労をした生き様も含めて、船で受けた傷跡を見せながら、事あるごとに子どもや孫たちに語って聞かせる父でした。イギリス軍の捕虜時代に覚えた片言の英語、「アイムソーリー」「サンキューベリーマッチ」は、晩年認知症になっても時々口にしていました。
苛酷な体験をしながらも、無事に生きて帰ってこられたからこそ今の私たちがある、今の平和を守り続けなければ、とつくづく思います。